親子で学ぶお金と社会の教養書|『きみのお金は誰のため』を読んで考えたこと

こんにちは。
今回の書籍は『きみのお金は誰のため』です。
お金の悩みのヒントを与えてくれる書籍ですので、是非読んで頂きたい1冊です。
「お金って、結局なんのためにあるの?」 「お金があれば幸せになれるの?」
そんな素朴な疑問に、心温まる物語で答えてくれるのが、田内学さんの著書『きみのお金は誰のため』です。
お金の本質、社会の仕組み、人と人のつながりまで——難しそうなテーマを、優しい語り口と物語形式で丁寧に紐解いてくれます。
「お金の本、また説教くさいだけ?」と思っていませんか?
『きみのお金は誰のため』はそうじゃありません。
これは、物語だからこそ心に響く、本当の“お金の教養”の物語――
● 中学生の優斗と“ボス”による、不思議な屋敷での学び。
● お金の謎がひとつずつ解き明かされる爽快感。
● 経済のしくみを自然と理解できて、読み終わると視界が変わる。
● 読者選出ビジネス書グランプリ受賞の信頼感。
● 今なら、漫画版も選択肢にあるから「読みたい形式」で楽しめる!
まずは目次だけでも…と軽い気持ちでめくってみてください。「どうやって?」から、「こういうことだったのか!」に変わる瞬間が訪れます。
👉【『きみのお金は誰のため』、中身をチラッと確認してみる】

『きみのお金は誰のため』とは?
本書は、ある少年が「ボス」と呼ばれる謎の人物に出会い、さまざまな「お金の謎」を通して世界の見方を変えていく物語。
まるで絵本のような語り口でありながら、その中身は非常に本質的で深く、読後に「世界が少しやさしく見える」感覚を残してくれます。
なぜ今この本が刺さるのか?
1. お金との向き合い方が問われる時代
FIREや資産形成が注目される一方で、「本当にそれだけでいいの?」と立ち止まる人が増えています。 物価高や将来不安が広がる中、「お金をどう貯めるか」ではなく、「どう使うか」「誰のために使うか」を改めて考える時期に来ているのです。 この本は、お金を“手段”として捉え直すことで、心の豊かさを取り戻すきっかけをくれます。
2. 分断ではなく“つながり”に目を向ける社会へ
SNSやメディアの影響で、「成功=稼ぐこと」「幸福=所有すること」といった価値観が強調されがちな現代。 そんな時代に、本書が描く「贈与」や「つながり」は、まさに逆風の中で灯る光のような存在です。 誰かのためにお金を使うこと、自分にできる形で分け合うこと——それらの行動が、今の社会に必要とされていると多くの読者が感じています。
3. 子どもと“お金の話”ができない親世代が増えている
金融教育が重視される一方で、「どこから話せばいいのか分からない」「難しい話は避けてしまう」という親世代は少なくありません。 本書は物語形式なので、子どもも大人も同じ視点で読み進められます。親子で「お金って何だろう?」と考える時間をつくれるという意味でも、“今”必要な一冊です。

本書のキーメッセージと実践法
1. お金は「ありがとう」を形にしたもの
お金とは、誰かに価値を届けた証。その背景には、他者に貢献したことへの感謝=「ありがとう」の気持ちが込められています。 この考え方は、日々の仕事や家事、ボランティアなど、報酬の有無にかかわらず、「誰かの役に立つ」ことに意味を見いだせるようになります。
つまり、お金を得ることだけが目的なのではなく、「ありがとう」を生み出す行動が本質だということ。 この価値観に触れると、仕事への向き合い方や消費行動にも、自然と変化が生まれます。
2. 貯めるだけでは意味がない
「将来が不安だから」「老後のために」と、多くの人が貯金を正義だと信じて疑いません。 しかし本書は、「みんなが貯めるだけになったら、社会はどうなる?」という視点を投げかけます。
お金は使ってこそ意味があり、社会に回すことで誰かの“ありがとう”に変わっていきます。
だからこそ、「貯める」ことと同じくらい、「使う」こと、「分け合う」ことも大切。計画的に、意義のある支出をすることで、社会の循環にも貢献できるのです。
3. 「格差」は敵ではない
格差問題は、現代社会の大きな課題の一つです。 けれど本書では、単純に「持つ者 vs 持たざる者」という構図ではなく、歴史や仕組みの延長としての格差を描いています。
敵を見つけて批判するのではなく、「自分にできること」「分かち合えること」を考えるきっかけを与えてくれます。
他人の失敗や貧困に対しても、「なぜそうなったのか」を理解しようとする想像力と優しさが育まれる—— これが、本書が示す“分断ではなく共感”の視点です。
4. 贈与こそが、未来の希望
最も強く訴えかけてくるのが、「贈与(ギフト)」の力です。 お金はただの取引手段ではなく、「誰かの幸せのために、自分の資源を分け与える行為」でもあります。
たとえば、親が子に「将来のために」と学費を払うのも、近所の人におすそ分けをするのも、すべて“贈与”です。 見返りを求めない贈り物こそが、人間社会の信頼やつながりを育て、次世代へと希望を繋げていきます。
このような視点を持てば、お金は単なる経済的価値ではなく、「心を届ける手段」として捉えられるようになります。
幅広い世代に響く3つの理由
10代・学生世代:お金に対する健全な価値観を育てられる
義務教育では教わりにくい「お金の意味」や「社会とのつながり方」を、物語を通じて自然に理解できます。
「お金は目的ではなく、ありがとうを渡す手段」——この視点を早い段階で身につけておくことで、将来のお金との付き合い方や職業選択において、大きな武器となります。
また、勉強や部活動、アルバイトなど、自分が関わる日常のすべてが「誰かのためになる行動」だと気づいたとき、自信と前向きな行動が生まれるでしょう。
30代〜40代:子どもや家族とお金の話ができるようになる
この世代は、子育て・住宅ローン・キャリアなど多くの責任を抱えながら、「お金=悩みの種」になりやすい年代。
本書を通じて「お金の本質」や「社会とのつながり方」を見直すことで、日常の中にある“やさしい使い方”や“贈る力”に目を向けられるようになります。
また、子どもと「お金の話をする」きっかけとしても最適。 難しい経済用語ではなく、物語を共有することで価値観を語り合える貴重な時間が生まれます。
50代〜60代:社会に何を残すかを考えるきっかけになる
この世代にとって、「お金をどう増やすか」よりも「何を残すか」が重要なテーマになります。
『きみのお金は誰のため』は、資産や地位ではなく「想い」や「つながり」をどう次世代に“贈る”かを考えるうえで大きな示唆を与えてくれます。
孫や若い世代への教育支援、地域活動への参加、趣味を通じた関係づくり——それらもすべて、贈与のかたち。
読後には、「自分の人生を通じて、どんな“ありがとう”を社会に残したいか」を自然と問い直したくなるはずです。
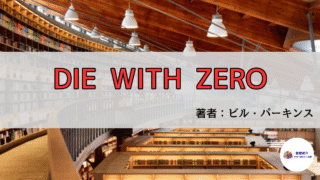
感想・レビュー:心に残ったフレーズ
「お金って、ありがとうを渡すための手段なんだよ」
この一言が、自分の中の“お金への執着”を溶かしてくれました。
これまで私は、「お金はもっと稼がなければいけない」「将来のためにとにかく貯めておかなければ」と思い込んでいました。買いたいものも、行きたい場所も我慢して、「いつか」のためにお金を貯めることばかり考えていたのです。
でもこのフレーズに出会ってから、「お金=ありがとうの橋渡し」という視点を持てるようになり、お金の使い方が大きく変わりました。
たとえば、ちょっとしたお菓子を職場の同僚に差し入れする、友人に手土産を持っていく、家族と外食に出かける——そういった小さな使い方にも、しっかりと「誰かの笑顔」というリターンがあることに気づきました。
それは見返りを期待していない“贈与”だけれど、自分の心も不思議と満たされるのです。
この本を読んで、お金を「ためる」から「回す」「贈る」という発想に切り替えることで、人生そのものの質が変わったように思います。
「もっと稼ぐ」ではなく、「どう使うか」——そこに、自分らしい豊かさがあるのだと気づかせてくれた一冊でした。
まとめ:やさしいお金の使い方が、やさしい社会をつくる
『きみのお金は誰のため』は、お金についての知識を教えてくれるだけでなく、私たちの「人生の軸」を整えてくれる一冊です。
本書を通して気づかされるのは、お金はただの「数値」ではなく、「誰かへのありがとう」を届ける手段であるということ。そしてその“ありがとう”が社会を循環させ、信頼や希望につながっていくということです。
大きなお金を動かす必要はありません。 今日、誰かに小さな贈り物をしてみる。 明日、自分のためにちょっといいランチを選んでみる。
そんな一つひとつの選択が、「自分らしいお金の使い方」となり、「やさしい社会」の一部になるのだと、本書は教えてくれます。
もしあなたが今、「このままでいいのかな」「お金の不安が尽きない」と感じているなら—— ぜひこの本を手に取って、自分とお金の関係を見つめ直す時間を過ごしてみてください。
きっと、これからの生き方が少しだけ軽やかに、そしてあたたかくなるはずです。








